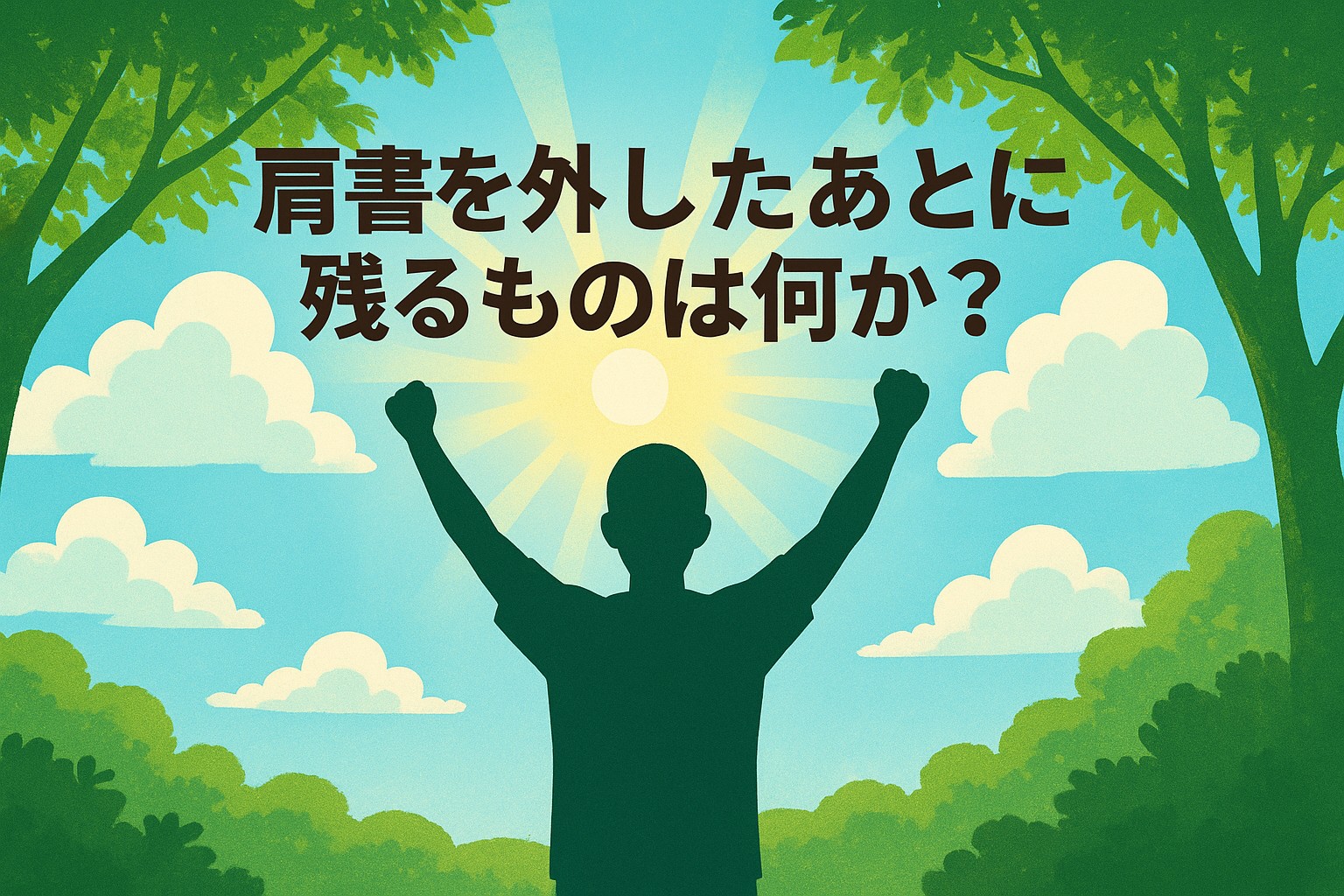長い間働いていると、名刺に書かれた肩書が自分そのもののように思えてしまいます。
けれど、いざその肩書を外した時、手元に残るのは何でしょうか。
肩書を失うことは「自分を失うこと」ではありません。
むしろそこからが本当の自分らしさを探す旅の始まりかもしれません。
今日は、私自身が感じてきた「肩書を外したあとに残るもの」について考えてみたいと思います。
肩書に頼りすぎていた自分
正直に言えば、私も長い間「〇〇会社の△△さん」という呼ばれ方に慣れていました。
人と会う時には名刺を差し出し、それが自分の存在を証明するような安心感を与えてくれていたのです。
けれど、肩書というのはあくまで「借り物」。それがなければ会話のきっかけすらつかめない自分に気づくと、少し怖くなったこともありました。
肩書は立派でも、中身の自分はどうなのか。
例えば、家族との時間、趣味の旅行での経験、地域での交流――これらには肩書なんて関係ありません。
そう考えると、肩書に頼りすぎていた過去の自分が少し恥ずかしく思えるのです。
本当に残るのは人とのつながり
昔、新聞配達をしていた頃のことをよく思い出します。
中学生だった私は、毎朝眠い目をこすりながら新聞を配り歩いていました。
当時の自分には肩書なんて一つもなく、ただ「近所のガキ」という存在でした。
でも、不思議と街の人から「おはよう」と声をかけられると、うれしかったものです。
その頃の記憶を思い返すと、やっぱり人との関係こそが一番大切なんだと感じます。
肩書がある時は、その立場のおかげでつながる人が多かったかもしれません。
しかし、肩書を外した後に残るのは「自分という人間をどう見てもらえるか」です。
結局は人柄や誠実さ、日々の小さな積み重ねが、その後の人間関係を作っていくのだと思います。
肩書よりも自分の価値観を大切に
私が大切にしている言葉に「これでいいのだ」があります。
赤塚不二夫さんの漫画の名セリフですが、肩書を外したあとの人生を考える時、まさにこの言葉がしっくりきます。
完璧でなくてもいいし、立派でなくてもいい。
大切なのは「自分らしくいられるかどうか」です。たとえば旅行が好きなら、無理のない範囲で行きたい場所に足を運んでみる。
映画に感動したなら、その余韻を大切に味わう。
肩書に縛られない時間は、そんな素直な気持ちを自由に表現できる貴重な時間だと思います。
シニアだからこそできる挑戦もある
シニア世代になると「もう新しいことは難しい」と思いがちです。
私自身も人見知りな性格で、新しい挑戦には腰が重いところがあります。
ですが、インドネシアでの海外勤務を経験した時、怖がらずに会話を続けることで道が開けた経験がありました。その体験から、「年齢を理由に挑戦を諦めるのはもったいない」と思うようになったのです。
たとえば、ちょっとした習い事や地域の活動に顔を出してみること。小さな一歩でも、新しい出会いや発見につながるかもしれません。
肩書ではなく「自分自身」で関わるからこそ、そこに本当の充実感が生まれるように思います。
残したいのは「ありがとう」と言える日々
肩書を外した後に残るものは、人とのつながり、そして自分の生き方だと思います。
私が一番感謝しているのは、健康でいてくれる家族の存在です。
名刺や役職を持っていなくても、「ありがとう」と素直に言い合える時間こそが、人生で何より価値のあるものなのだと実感します。
これから先の人生、肩書がなくても「ありがとう」を交わせる人たちに囲まれて過ごせるようにしたい。
そのために、今日一日をどう過ごすかを大事にしていきたいと思います。
まとめ ― 肩書を外したあとの人生は自由だ
肩書を外したあとに残るものは、結局「自分らしさ」と「人との関係」ではないでしょうか。
名刺や役職がなくなっても、自分の価値はなくなりません。
むしろ、そこから本当の自分を生きる時間が始まります。
もし同じように肩書の先に不安を感じている方がいれば、こう考えてみてください。
「肩書を失ったら自由になれる」と。
シニア世代だからこそできることはたくさんあります。
新しい趣味を見つけてもいいし、地域や家族と深く関わるのも素敵です。
これからの人生を、自分らしく楽しむために。肩書を外したあとこそが、本当のスタートラインなのかもしれませんね。